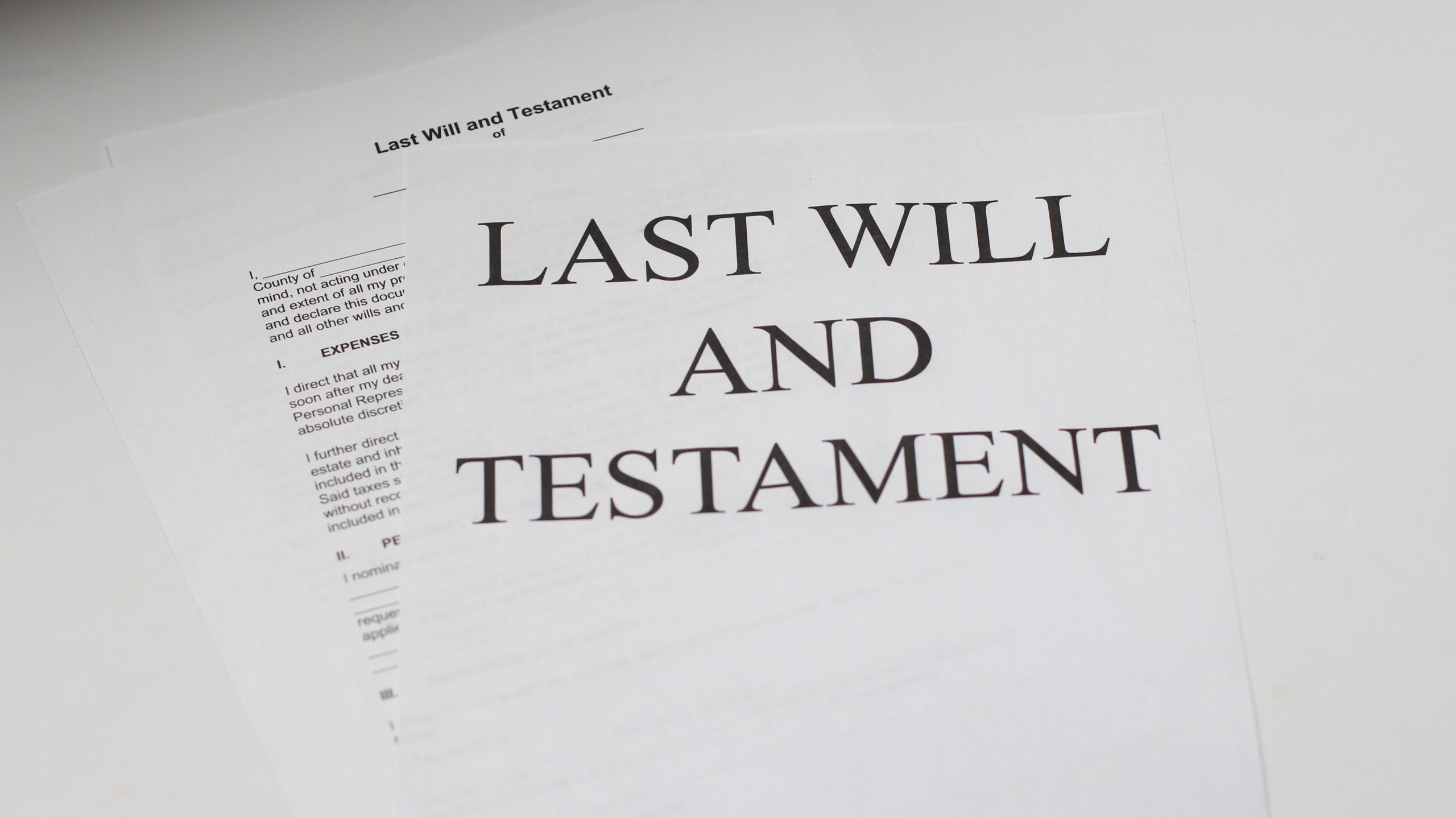通常遺産を取得するのは相続人です。しかし、相続人以外に取得させることも可能です。典型的な手段は遺言です。生命保険金や死亡退職金の受取人を相続人以外の人にすることでも目的を達成できます。
自分が亡くなった後でどうしても遺産を受け取って欲しい人が相続人以外にいる場合には、こうした手法を用いることになります。しかし、相続人以外の人が遺産を受け取ることで税金の面で不利な取り扱い受けることがあります。 そのような不利な取り扱いの代表例を紹介します。
相続人以外の人に適用される相続税の不利規定
相続税額の2割加算
相続または遺贈により財産を取得した人が次に掲げる人以外の人である場合には、その人の相続税額は、通常の算出税額にその20%に相当する金額を加算した金額とします (相続税法18条) 。
- 被相続人の一親等の血族(その被相続人の直系卑属でその被相続人の養子となっている人(いわゆる孫養子の類)を除く。ただし「2」のケースはこの限りでない)
- 被相続人の直系卑属が相続開始前に死亡し、または相続権を失ったため、代襲して相続人となったその被相続人の直系卑属
- 配偶者
この規定は、相続人であっても場合によっては適用されてしまうような制度設計になっていますので、相続人以外の人には当然のように適用がありえます。
平均税率が低い場合にはそれほどの痛手にはなりませんが、平均税率が高い場合には相応の痛手になりかねません。例えば、平均税率5%なら2割増しで6%となり1ポイント上昇ですみますが、平均税率が20%ならば2割増しで24%となり4ポイントも上昇します。
相続人以外の人が適用を受けられない相続税の有利規定
生命保険金の非課税・退職手当金等の非課税
受取人が相続人の場合
被相続人の死亡により相続人が死亡保険金を受け取った場合には、その保険金受取人が、その保険金のうち被相続人が負担した保険料に対応する部分を、被相続人から相続により取得したものとみなされます(相続税法3条1項一号)。
被相続人の死亡により相続人が被相続人に支給されるべきだった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与で被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものの支給を受けた場合には、その退職手当金等の受取人がその退職手当金等を被相続人から相続により取得したものとみなされます(相続税法3条1項二号)。
このようなみなし規定が設けられている理由は次のとおりです。
形式的な民法上の観点からすると、保険金受取人が保険会社から保険金を受け取ることは相続による財産の取得とはなりません。同様に、被相続人の勤務先から退職手当金を受け取ることも、民法上の相続による財産の取得とはなりません。
しかし、実質的には、これらの財産の動きは被相続人からの相続による財産の取得と変わりません。そうであれば、これらも相続税の課税の対象に組み入れるべきということになります。そうしないと簡単に相続税の課税を回避することができてしまい、課税の公平が保てなくなります。
他方、こうして相続人が相続により取得したものとみなされた生命保険金や退職手当金等について、直ちに全額が課税されることはありません。それぞれ、500万円に法定相続人の人数を乗じた金額を非課税限度額とし、その枠を超える部分にのみ相続税を課すことにしています(相続税法12条1項五号六号)。
受取人が相続人以外の場合
被相続人の死亡により相続人以外の者が死亡保険金を受け取った場合には、その保険金受取人が、その保険金のうち被相続人が負担した保険料に対応する部分を、被相続人から遺贈により取得したものとみなされます(相続税法3条1項一号)。
被相続人の死亡により相続人以外の者が被相続人に支給されるべきだった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与で被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものの支給を受けた場合には、その退職手当金等の受取人がその退職手当金等を被相続人から遺贈により取得したものとみなされます(相続税法3条1項二号)。
このとき、相続人であれば使えた非課税限度額の規定は、相続人以外の者には適用されません。すべて相続税の課税対象になります。
未成年者控除
相続または遺贈により財産を取得した者(外国に住んでいるなどの一定の特殊なケースの人を除きます)が被相続人の相続人であり、かつ、20歳未満である場合には、次の算式の控除額を控除した金額をもって、その納付すべき相続税額とします(相続税法19条の3)。
算式:その人が20歳になるまでの年数×10万円
このように相続人であることが要件になっていますので、相続人以外の人が20歳未満であったとしても未成年者控除は使えません。
障害者控除
相続または遺贈により財産を取得した者(外国に住んでいるなどの一定の特殊なケースの人を除きます)が被相続人の相続人であり、かつ、障害者である場合には、次の算式の控除額を控除した金額をもって、その納付すべき相続税額とします(相続税法19条の4)。
算式:その人が85歳になるまでの年数×10万円(特別障害者の場合には20万円)
このように相続人であることが要件になっていますので、相続人以外の人が障害者であったとしても障害者控除は使えません。
相次相続控除
相続人が被相続人から相続または遺贈により財産を取得した場合において、その被相続人がその相続開始前10年以内に相続により財産を取得したこと(あるいは、相続人に対する遺贈として財産を取得したこと)があるときは、その相続人については、一定の控除額を控除した金額をもって、その納付すべき相続税額とします(相続税法20条)。
ここでも相続人であることが要件になっていますので、10年以内に相次いで相続の開始があった場合でも相続人以外の人は相次相続控除を使えません。
農地についての相続税の納税猶予
一定の条件を満たす農業を営んでいた人の相続人が、相続又は遺贈により一定の条件を満たす農地等の取得をした場合には、本来納付すべき相続税の額のうち一定の納税猶予分の相続税額について、農業の継続や担保提供などを条件に、納税猶予期限までその納税が猶予されます(租税特別措置法76条の6)。
ここでも相続人であることが要件になっていますので、相続人以外の人は農地についての相続税の納税猶予を使えません。
相続人・包括受遺者以外の人が適用を受けられない相続税の規定
債務控除
相続税は正味財産に課税することとしているため、財産の価額から債務の金額を控除することができます。また、葬式費用についても、これは厳密には被相続人の債務ではありませんが、被相続人の死亡により発生する費用であり相続財産のなかから支払う意識が高いことから、債務控除の一環として同様な控除が認められています。
ただし、こうした債務控除を受けることができるのは、相続人と包括受遺者だけです。その理由は、相続人と包括受遺者は被相続人の権利と義務の両方を承継する立場にあるからです。
【用語】包括受遺者とは――
遺言で財産を取得させることを遺贈といいますが、遺贈には「特定遺贈」と「包括遺贈」の2つのタイプがあります。
特定遺贈は、遺贈の対象となる財産を個別に特定するタイプの遺贈です。例えば、あの土地はAさんに、この建物はBさんに、といった具合です。
包括遺贈は、遺贈の対象となる財産を個別に特定しないタイプの遺贈です。例えば、すべてAさんに、ですとか、全体の3分の2をAさんに残りの3分の1をBさんに、といった具合です。この包括遺贈の場合、財産とともに債務をも“包括的に”引き継ぐことになります。この包括遺贈により財産債務を承継する人のことを包括受遺者といいます。
いっぽう、特定遺贈においても、被相続人の債務を承継することを条件に財産を取得するという方式――これを「負担付遺贈」といいます――により、被相続人の債務を承継することがありえます。この場合には、その債務についての債務控除は出来ないことになります。
ただし、このとき債務控除はできないものの、負担付遺贈により取得した財産の価額は、負担がなかったものとした財産の価額からその負担額を控除した価額となります(相続税法基本通達11の2-7)。よって、負担付遺贈に係わる財産の相続税評価額がそれに対応する負担額よりも大きい場合には、実質的に債務控除をうけたのと同じ結果になります。しかし、その大小関係が逆の時は、財産の評価額がマイナスになることはありえないことから、控除しきれない部分が生じてしまうという不利益が考えられます。
さらに、こうした負担付遺贈は被相続人の譲渡所得の課税原因になるという論点がありますので、所得税をも巻き込む煩雑な税務手続きが必要なってしまうというデメリットもあります。
相続人以外の人に債務を承継してもらう構想がある場合には、税務的な観点からは、できるだけ包括遺贈の形になるようにしたほうが無難と言えそうです。